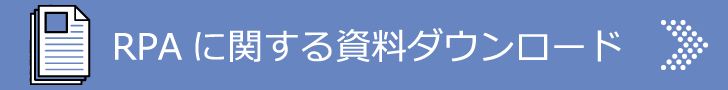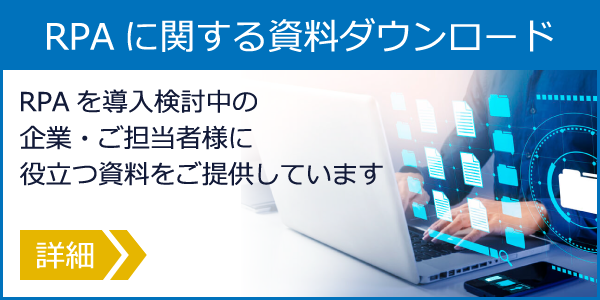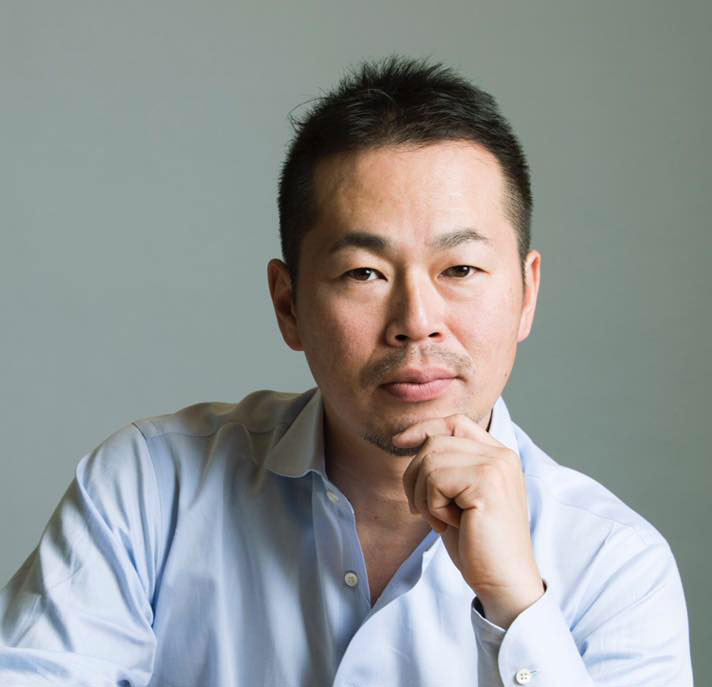多くのビジネス現場で活用され、業務効率化や生産性向上、コスト削減などの効果を上げているRPA。とはいえ、実際にどのような業務ができるのか、イメージがつかない方もいるでしょう。
そこで本記事では、RPAツールにできることとできないことをご紹介します。RPAツールができることを理解すれば、自社のビジネスプロセスの業務効率化のイメージも想像しやすくなるはずです。ぜひ参考にしてみてください。

- 1. RPAでできることまとめ
- 1.1. その①:決められたことを繰り返し行う定型業務
- 1.2. その②:大量データの処理
- 1.3. その③:データ収集・集計・加工
- 1.4. その④:複数アプリケーション間での同時処理
- 1.5. その⑤:問い合わせ対応
- 2. RPAでできないことまとめ
- 2.1. 都度判断が必要な業務
- 2.2. 複雑な処理が求められる業務
- 3. RPAでできること・業務の身近な例は?
- 3.1. 請求書などの発行
- 3.2. 問い合わせ対応
- 3.3. 在庫管理
- 3.4. 日次・週次・月次レポートの作成
- 4. おすすめのRPAツール
- 5. RPA化の対象業務を選ぶ方法
- 5.1. ステップ①:現行業務の洗い出し
- 5.2. ステップ②:自動化できそうな業務の選定
- 5.3. ステップ③:自動化対象業務の決定
- 6. RPAでできることは定型業務
RPAでできることまとめ

RPAはさまざまな業務を自動化でき、特に「単純かつ定型の業務を自動化/効率化すること」を得意としています。その得意なことを活かすことが出来るのは以下の5つの業務です。
- その①:決められたことを繰り返し行う定型業務
- その②:大量データの処理
- その③:データ収集・集計・加工
- その④:複数アプリケーションでの同時処理
- その⑤:問い合わせ対応
1つずつ解説していきます。
その①:決められたことを繰り返し行う定型業務
RPAは手順が決められている単純かつ、定型の業務の自動化を得意としています。
具体的な例を挙げると以下のような業務が当てはまります。
- 伝票内容をシステムへ転記する
- 複数のシステムから情報を取得して、1つにまとめる
業務を行う上でマニュアルがあって、書かれている通りに判断/処理する業務であればRPA化できます。
決められたことを繰り返し処理し続けるのは人間の苦手な分野ですが、逆にRPAは得意としている分野です。
その②:大量データの処理
RPAは、大量データの処理を得意としています。
入力やデータ加工を行う作業スピードについて人間とRPAとで比較すると、RPAのほうが早く処理できます。
さらに、労働時間に関係なく実行することが可能であり、深夜や早朝などの業務時間外でも継続して処理を続けることが可能です。
また、入力処理の正確さもRPAのほうが高く、入力ミスおよび、入力ミスから発生する手戻りや業務影響がなくなります。
このような大量データの処理はRPAが向いています。
その③:データ収集・集計・加工
RPAはデータの収集とその集めたデータの集計/加工を得意としています。
データ収集では、以下のような情報の取得処理をRPAに任せることができます。
- Web上で販売されている商品の価格
- 為替相場や株の価格
- 自社に関連するニュース
また、取得したデータをExcelに貼り付けて、社内メンバーへメールで展開するというようなことまですべてを、RPAで自動化できます。
これらの処理をスケジュール化することで毎日、毎週、毎月などの希望のタイミングで自動的に処理させることができます。
その④:複数アプリケーション間での同時処理
RPAは、既に用意されているシステムの機能をそのまま操作/利用できるかつ、複数のアプリケーションを同時に使って処理を進めることが得意です。
具体的には以下のような業務です。
- 受信したメールの内容をExcelへ転記する
- Webで確認したデータを基幹システムへ登録する
- 複数のシステムからデータを取得して報告書をまとめる
日常業務ではメールやExcel、Webブラウザ、基幹システムなど複数のアプリケーションを使って処理を行っていくことが多いです。これらを使った業務を1つのアプリケーション内にとどまらず、複数のアプリケーションをまたいで自動化できることがRPAの強みとなります。
その⑤:問い合わせ対応
RPAは就業時間に制限されず、24時間ずっと動くことができるため、顧客からの問い合わせがいつ来たとしても返答できます。
RPAを以下のように利用することで、RPAと人間が共同で問い合わせ対応を行うというハイブリッドな運用が実現できます。
- よくある問い合わせの場合:RPAのロボットが判断した上で自動返信を行う
- 上記以外の場合(RPAで判断が難しいケース):担当者へメールやチャットなどでエスカレーションする
RPAを導入することで、問い合わせ対応に使う作業時間を減らして、人にしかできない業務にシフトできます。
RPAでできないことまとめ
RPAを導入することで大きな効果を生み出せる一方で、導入しても効果が出にくいRPAに向いていない業務もあります。
RPAに向いていない業務は以下の2つです。
- その①:都度判断が必要な業務
- その②:複雑な処理が求められる業務
1つずつ説明していきます。
都度判断が必要な業務
毎回状況が違って、都度判断が求められる業務はRPA化することは向いていません。
上記でもお伝えした通り、マニュアルが作れるほど判断基準が明確になっている業務はRPA化に向いています。
ただ、数字だけでは判断できない、そもそも数値化できないような情報を見て判断する業務では、判断基準が不明確になるためRPA化することが難しいです。
上記のような都度判断が必要なケースでは、判断する業務のみ人間が処理し、それ以外をRPA化するケースが多いです。
複雑な処理が求められる業務
明確な基準はあるものの、実装するケース(分岐)が多すぎて複雑になっている業務もRPA化に向いていません。
実装するケース1つずつは単純で簡単だったとしても、それぞれの処理毎にロジックを作る必要があるため、メンテナンスが大変です。
また、ルールが多すぎると確認が難しくなり、手順が誤っていたとしても気づけない場合があります。
こういった複雑な業務をRPA化する場合は、業務のパターンの見直しと、シンプル化を実施してからRPAを導入すると効果が出やすいです。
RPAでできること・業務の身近な例は?
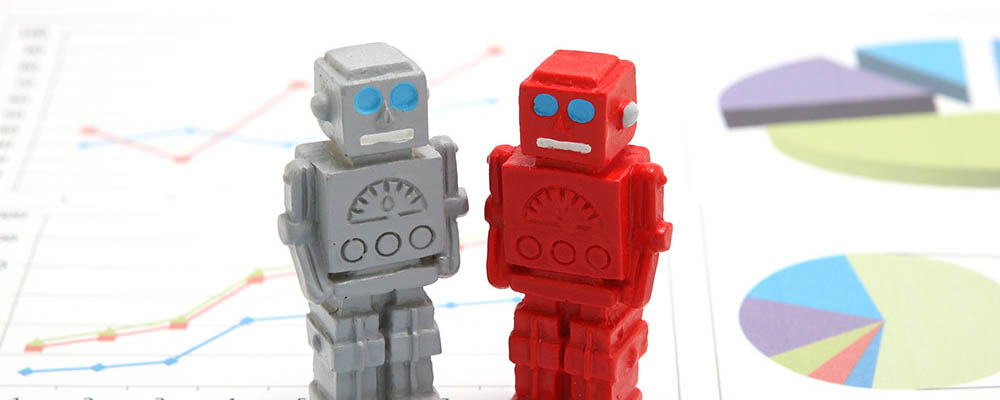
RPAでできることとできないこと、その概要についてお話しさせていただきましたが、まだ具体的なイメージがつかみにくいという方もいるでしょう。そこで以下、より具体的な業務イメージに沿ってRPAでできることをご説明します。
請求書などの発行
毎月定期的に発行しなければならない請求書や発注書、見積書などの発行はRPAで自動化しやすいです。データをExcelなどに集計してデータベースに保存し、それらのデータを加工して請求書などの帳票を発行し、さらにその帳票をメールやチャットなどで送付するところまで、すべて自動化可能です。
ただし、RPAで自動化できるのはあくまで定型的な業務だけなので、すべての帳票作成・送付業務を自動化できるわけではありません。
問い合わせ対応
問い合わせ対応もRPAツールを用いれば、ある程度までは自動化可能です。例えば、フォームからの問い合わせ対応については、自動応答できる部分は自動応答で返し、それ以外は人によって応答するなどして効率化できます。決まった質問・回答について自動で対応することで、大幅な業務効率化が実現できることでしょう。
フォームだけではなく、電話サポートについても同様です。決まったパターンの質問・回答については自動化できます。
在庫管理
ルーティーン作業が多く、人手でやるには業務効率が悪いにもかかわらず、重要な業務が在庫管理です。まさに、RPAツールによって業務効率化がしやすい分野の仕事と言えます。
RPAツールを用いることで、在庫数や出荷予定数をあらかじめ決められたタイミングで担当者にメールなどで通知することができます。担当者はその通知を見て発注などの指示を適切なタイミングで出すことができます。そうすることで、余計な業務を削減し、業務効率化が可能です。
日次・週次・月次レポートの作成
あらかじめ決められた時期に決められたデータを用いてレポートを作成する業務は、RPAツールが最も得意とする業務のうちの1つです。日次・週次・月次のそれぞれの期間ごとに発行するレポートを自動で作成できるだけでも、大幅な業務効率化につながることでしょう。
データをそのまま出力するだけではなく、グラフを作成して出力もできるので、後で人がレポートを見ながら分析する作業も容易になります。
おすすめのRPAツール
自社にRPAツール導入を考えている方には、「WinActor」の導入がおすすめです。「WinActor」はNTTグループが研究開発したRPAツールなので、国内ビジネスの商習慣などを踏まえて使いやすい作りになっています。純国産ツールなので、わからないことがあった際にも問い合わせがしやすいです。
ExcelなどのOfficeソフトはもちろんのこと、ブラウザやメールなど、さまざまなアプリケーションに対応しています。そのため、複数のアプリにまたがる作業自動化も可能です。
RPA化の対象業務を選ぶ方法
ここからは、実際にRPA化する業務の選び方についてお伝えします。
RPA化する業務を選定する方法は、以下①~③のステップを順番に進めていくと失敗を少なくできます。
- ステップ①:現行業務の洗い出し
- ステップ②:自動化出来そうな業務の選定
- ステップ③:自動化対象業務の決定
1ステップずつご紹介していきます。
ステップ①:現行業務の洗い出し
まずは、日常的に行っている業務を洗い出し、普段からどういった業務を行っているのかを洗い出していきます。
洗い出す際には以下の業務が見落としがちになるため注意が必要です。
- 定型的なデータ抽出
- 決まりきったメールの返信
RPAは上記のような単純かつ、定型的な処理を得意としています。
人だと簡単すぎて洗い出しから漏れがちになるすべての工程を意識して収集することを心がけてください。
なお、業務を洗い出す際には、その業務では何をしているのか誰でもわかるように、業務概要や業務フローを簡単でもよいので書いておくことをおすすめします。
ステップ②:自動化できそうな業務の選定
現行業務の洗い出しが完了したら、その中から自動化が出来そうな業務を選定します。
大前提として、RPAはパソコン上で動かすため、パソコンで作業をする業務である必要があります。
その上で、業務手順が決まっていれば自動化できます。
RPA化できるか判断する方法の1つとして、その業務にマニュアルが存在するかどうかで判断ができます。
マニュアルがある=手順や処理ルールが決まっているためです。
上記のような観点から、自動化できそうな業務を選定してください。
ステップ③:自動化対象業務の決定
自動化が出来る業務の選定ができたら、RPAの導入効果が高
RPAを導入して特に効果が出やすいおすすめの業務は、以下の特徴がある業務です。
- 単純かつ簡単な処理を繰り返す
- 大量データの処理
上記は、人が処理すると長時間同じ作業を繰り返すことで、飽きや疲れが出てミスが発生しやすい業務です。
RPAは疲れることがなく、1つずつ着実に処理を進めていきます。
人とRPAに明確な差が出る業務なので、RPA化におすすめの業務です。
RPAでできることは定型業務

以上、RPAでできることとできないことをまとめてご紹介しました。
RPAでできることは、定型的な業務です。つまりRPAは、段取りが決められているようなルーティーン業務の業務効率化が得意です。例えば、請求書や見積書などの発行や送付、レポートの発行、在庫管理などの分野での業務には大いに威力を発揮します。
逆にRPAでできないことは、非定型的な業務です。ルールやフォーマットが断続的に変化していくような業務では、RPAは利用できません。
記事でご紹介した事例だけではわからないこともあるでしょう。「自社ビジネスをRPAで変革したい」「でもRPAでできることがイマイチわからない」とお考えの方はぜひお気軽にお問い合わせください。